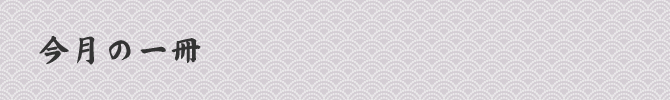
 子どもの頃から本が好きで、暇さえあれば読んできました。
子どもの頃から本が好きで、暇さえあれば読んできました。
毎月一冊、これまでの読書の中で印象に残った本をご紹介させていただきます。
- 2010年12月『 武士道と日本型能力主義 』 笠谷和比古 著
- 2010年11月『 老いの才覚 』 曽野綾子 著
- 2010年10月『 百姓の江戸時代 』 田中圭一 著
- 2010年 9月『 武家の女性 』 山川菊栄 著
- 2010年 8月『 海からの贈り物 』 リンドバーグ夫人著・吉田健一訳
- 2010年 7月『 江戸の子育て 』 中江和恵 著
- 2010年 6月『 江戸に学ぶ「おとな」の粋 』 神埼 宣武 著
- 2010年 5月『 せんたくかあちゃん 』 さとう わきこ 作・絵
- 2010年 4月『 名ごりの夢 蘭医桂川家に生れて 』 今泉みね著・金子光晴解説
- 2010年 3月『 いのちをいただく 』 内田美智子著・佐藤剛史監修・諸江和美 絵
- 2010年 2月『 仏陀のおしえ 』 友松圓諦著
- 2010年 1月『 逝きし世の面影 』 渡辺京二著
2010年12月『 武士道と日本型能力主義 』 笠谷和比古 著

固定的な身分社会と思われていた江戸時代だが、実は藩主が家臣に更迭される「主君押込」や、有能な下級武士を抜擢する能力主義が機能していた。武士道の根本規範は、滅私奉公ではなく自立の精神と組織の繁栄追求であることを明らかにし、徳川吉宗、上杉鷹山の改革や、幕末の幕府官僚の例を挙げて、新しい武士像を提示する画期的な組織論。…と裏表紙に書かれています。
集団に埋没してしまうことのない個人の自立、武士の個人としての完成が武士道の目指すところであったとあり、これまでの武士道精神や江戸時代の武士社会への理解が一新されました。現代の日本の企業の組織にとっても参考になりそうな素晴らしい一冊です。
新潮選書 新潮社 2005年7月 1,365円
2010年10月『 百姓の江戸時代 』 田中圭一 著

年の取り方を知らない老人が急増してきた!超高齢化の時代を迎える今、わがままな年寄こそ大問題。自立した老人になり人生を面白く生きるための7つの才覚の持ち方。…と帯に書かれています。
「人間は死ぬまで働かなくてはいけない」、「分相応、身の丈に合った生活をする」、「老年の仕事は孤独に耐えること、その中で自分を発見すること」など、胸に響く言葉が随所にありました。
辛口の本ですが、これからの生き方を考える参考になりました。
“老い”は、まだ遠い先と思われる若い方々にもお薦めの一冊です。
ベスト新書 KKベストセラーズ 2010年9月 800円
2010年10月『 百姓の江戸時代 』 田中圭一 著
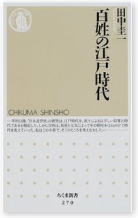
江戸時代は士農工商の時代だ、という常識がある。きびしい身分制度のもと、農民は田畑の所有を許されず、重い年貢に苦しめられ、自給自足を強いられたという説明だ。だが、村々に残る資料をみて歩くと、まったく異なる世界がみえてくる。百姓たちは銭を用いて布を買い、それを身にまとって祭りを盛り立てた。また、広い敷地に庭を造り、茶・書・華をたしなみ、俳句をよんで旅をした。その一方で、乏しい資源を大切にし、浪費を抑え、そして元気よく働いた。本書では、これまでの権力の側からの史観を覆し、当時の庶民である百姓の視点から江戸時代の歴史をよみなおす。… と裏表紙にありました。
新潟県の佐渡地方を中心に、知恵と元気によっていきいきと生きのびた農民の姿が描かれています。
学校の歴史の時間に習った「江戸時代」とは、違う「江戸時代」があったようです。驚きながら、読みました。
農村の歴史の勉強もしてみたいと思いました。
ちくま新書 筑摩書房 2000年11月初版 720円
2010年 9月『 武家の女性 』 山川菊栄 著

幕末の水戸藩の下級武士の家に生れ育った母・千世の思い出話をもとに、武士の家庭と女性の日常の暮らしをいきいきと描きだした庶民生活誌。動乱に明けくれる苛酷な時代の中で精一杯生きぬく女たちが巧みな筆致で描かれる。女性解放運動のすぐれた思想家であった著者が、戦時下の閉塞状況の中で書き下ろした名著。 (解説=芳賀 徹)…と表紙には書かれています。
昔の人たちの、凛とした生き方が伝わる一冊です。
人も物も大事にしながら、質素に、丁寧に、暮らしていた当時の様子が随所に伺えます。
激動の時代を、志高く、誇りをもって生きた女性たちがたくさんいたことに感動しました。
岩波文庫青162‐1 岩波書店 1983年4月初版 630円
2010年 8月『 海からの贈り物 』 リンドバーグ夫人著・吉田健一訳

〈大西洋横断飛行に最初に成功した飛行家リンドバーグ大佐の夫人であり、自らも世界の女流飛行家の草分けの一人である著者が、その経歴を一切捨て、一人の女として、主婦として、自分自身を相手に続けた人生に関する対話である。ほら貝、つめた貝、日の出貝などの海辺の小さな芸術品に託して、現代に生きる人間ならだれでもが直面しなければならぬいくつかの重要な問題が語られる。〉と、裏表紙の紹介されている100ページとちょっとの本です。
都会を離れ、家族を離れ、日常の生活から離れて、海辺に滞在した著者が
静かに自分自身と向き合う話です。
「本当に必要なもの」が浜辺に打ち寄せられた貝殻を通じて語られて行きます。
10数年前この本に出会って以来、何度となく読み返してきました。
何かわからないけれど疲れを感じる時などに読むと、きれいな浜辺で潮風に吹かれたような気持ちになり、落ち着きます。
手仕事をする時間の豊かさが伝わる個所もあり、 不器用で針仕事や編み物など普段は滅多にしない私でも(^^; 読後に、針や編み棒が持ちたくなります。
新潮文庫 新潮社 1967年7月初 420円
2010年 7月『 江戸の子育て 』 中江和恵 著

序に変えて 江戸の子育ては一日にしてならず
江戸時代―戦争のない安定した社会の中で、それまで受け継いできた文化を発展・成熟させ、広く庶民にゆき渡らせた二百六十余年。現在のような工業生産品こそなかったが、自然の素材を無駄なく使い、生活を豊かにしていった時代。そして何よりも、仕事に追われることなく、ゆったりと流れる時間の中で、大人も子どもも物語や本に親しみ、芝居を見、祭りを楽しんでいた。子どもたちは様々な遊びを案出し、大人は子どもを喜ばせる小さな玩具をたくさんつくった。…で始まるこの本では、常に子どもを見守り、かまい、子どもと睦み合う江戸時代の大人たちの姿が描かれています。
当たり前のこととして子どもと遊び、子どもを見守る
子煩悩で、教育熱心だった江戸時代の大人たち。
厳しい面もあったようですが、人間味があり、どこか楽しそうでもありました。
ゆとりがなくなってしまった現代の日本の子育てとの違いを随所に感じた一冊です。
文春新書315 文芸春秋 2003年4月初版 714円
2010年 6月『 江戸に学ぶ「おとな」の粋 』 神埼 宣武 著
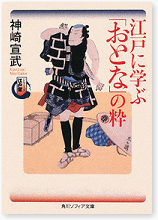
上方では「すい」、江戸では「いき」とよび、江戸人が理想とした大人ぶりの「粋」。金さばきがよく、「ほど」を心得、こざっぱりと身ぎれいにし、始末の美学をもち、見栄を張ってでも通人であろうとした江戸っ子。信心、旅、おしゃれ、遊びなどに通底する「粋」の心根に触れながら、現代では忘れられた、処世の法としての「粋」を学ぶ。宵越しの金はもたず、いなせで気っ風がいい、野暮は言いっこなしの大人になるための1冊 … と背表紙には書かれています。
「おとな」になれるか、なれないかは別として、江戸の人々の大事にしていたもの、価値観がよく伝わって来ます。
「ほどのよさ」を大切にした、庶民の暮らしぶりに魅力を感じました。
この本だけでなく、『「うつわ」を食らう』、『江戸の旅文化』など、民俗学者神埼先生の著書はどれも奥行きが深く、面白くて、勉強になります。
角川ソフィア文庫 シリーズ江戸学 2008年9月初版 620円
2010年 5月『 せんたくかあちゃん 』 さとう わきこ 作・絵
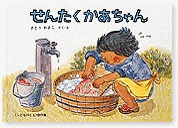
息子たちが小さかった頃、よく読んで聞かせた絵本です。
主人公の「かあちゃん」の元気さ、明るさが、たまりません。(^^)
理屈抜きで楽しい、子どもにも、大人にもお薦めの一冊です。
福音館書店 《こどものとも》傑作集 1978年8月初版 840円
2010年 4月『 名ごりの夢 蘭医桂川家に生れて 』 今泉みね著・金子光晴解説
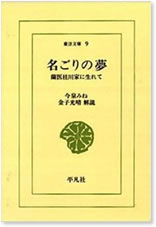
昔ある席で、いいお香を聞かせていただいたことがありました。
強い香りではないのですが、心地がよくて何とも言えない余韻がありました。
この本を読み終えた時も、香と本では、全く違う世界なのですが、同じような感じを受けました。
“幕末維新史の珠玉”と呼ばれる、作品です。
将軍家に蘭方医として仕えた桂川家に生まれた方が、子ども時代、娘時代を振り返ってお話したものをご家族がまとめたものです。
御典医として仕えた将軍家の素顔、蘭学の中心的な存在だった桂川家に集まった人々や御維新前後の江戸の様子などが、美しく品の良い言葉で語られています。
巻末の解説の中で、金子光晴氏は、「今泉みねの『名ごりの夢』は、控え目に語ることで、どちらへも片寄らない江戸と、話しかければすぐにこっちをふりむきそうな近い場所で、江戸人の顔々をうかびあがらせ、僕らの偏見や、誤った先入観を訂正してくれる。」と書いておられます。
時々読み返し、幕末の江戸に思いを馳せています。
平凡社 東洋文庫9 1963年10月初版 2,415円
2010年 3月『 いのちをいただく 』 内田美智子著・佐藤剛史監修・諸江和美 絵

白い表紙の小さな本です。 最初の三分の二は、やさしいイラストのふりがなつきの絵本で、食肉センターで働く坂本さんとその息子さんのおはなし。 後の三分の一が「いただきますということ」という文と写真からできています。 あっという間に読むことができる小さな本ですが、大切なことを気づかせてくれました。食べ物をたべることは、他の生き物の命をいただくこと。 そのことが静かに、厳しく、そして温かく伝わります。 読み終わった時、「ありがたい」という気持ちが自然に湧いてきました。
本の帯に、「朗読を聴いて、うちのムスメが食事を残さなくなりました」という主婦の方からの感想が書かれていますが、私も、食べ物を粗末にできなくなりました。 小さな子どもさんだけでなく、あらゆる方々にお薦めしたい一冊です。
西日本新聞社 初版2009年5月 1,280円
2010年 2月『 仏陀のおしえ 』 友松圓諦著
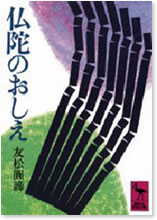
戦前、亡き祖父が深川三好町で開かれていた著者の勉強会に通っていたことを伯母から聞き、読みました。20年以上前のことです。以後、いつも傍らに。
正直なところ、判らないことがたくさんあります。ただ凡婦の私にも友松圓諦師の深い智慧と熱い想いは伝わってきました。
上手にご案内できないので、裏表紙にあった文章をそのまま下記に。
『著者は、明治・大正・昭和を通じ、二千五百年の伝統ある仏教を、再び世に活かしえた天才であった。本書は、実践と学問を通じて現代人の真の仏教とは何かを把握した著者が、日本仏教諸宗派を総括し仏教の内容をなす三つの不変なるもの、すなわち、仏・法・僧の「三宝」を中心にして、仏陀のおしえの根本義を誰にでも理解できる平易な言葉で著した最高の仏教入門書である。仏教という巨大なおしえの最重要の問題点が説かれている。』
読み始めたら止まらず、疲れたのでソファーに寝そべりながら読み続けていたのですが。最後のところでは、感動し、ソファーから落ちて正座をして読みました。
最終ページには、
『 … 施も戒も、ここでは小乗利己の行為ではなくして、ひとしく、法界に供養せられ、菩薩行、仏行として新たなる意味をもってくる。この菩薩利他の聖業のこそ、自分のかりそめの一身一命を乗托したい。この有限な、ほんの一断片がどうか仏行の一分として仏陀において意味のあるようにと願う。どうか、この偶然生まれきたった自分の有機体をば、人々との協力によって、この地上における浄土建立のためのひとつの意味のある者とならしめたい。ここに私たちは、現代社会をただずっと見つめていることのできない、捨てては置けない心のおどりと興奮をいただいて起ったことができ、しかも、いつでも、明日でも、今日でも、さては、この一瞬後にでも、安住した心持ちで淋しいながら、ほほえみを浮かべて死んでいける。』(昭和八年九月五日朝、大宮盆栽村にて)とありました。
「利他」という言葉が心に沁みる、大切な一冊です。
講談社 学術文庫 489 1980年9月初版 1,050円
2010年 1月『 逝きし世の面影 』 渡辺京二著
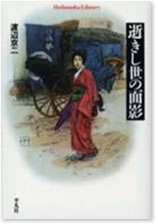
明治の“文明開化”の前に在った文明。江戸文明とか徳川文明とか俗称される、18世紀初頭に確立し、19世紀を通じて存続した古い日本の生活様式が幕末から明治にかけて来日したたくさんの外国人の記録を手掛かりにして浮き彫りにされています。
ある文明の幻影、陽気な人々、簡素と豊かさ、親和と礼節…、子どもの楽園、…14の章からなる読みごたえのある本で、「注」や「参考文献」もしっかりと記されています。江戸のことが知りたい私にはとても有難い本です。
この本に出会う前は、平凡社の東洋文庫などを主に一冊、一冊、外国人の日本紀行文を読んで興味のある部分を探していました。「逝きし世の面影」には、渡辺氏の鋭い視点で捉えた江戸に関する“エッセンス”が山のように記載されています。
これまで、学校で習った江戸時代や、テレビや映画で想像していた江戸のイメージと全く違う、おおらかで明るい、笑顔にあふれた江戸時代、物はなくても満ち足りていた当時の日本の姿が浮かんできます。読み始めると、面白く、電車の中でも夢中になってしまいます。繰り返し読んでいるのですが、車内で読んで、乗り越しそうになったことが何度も。都営三田線では、車庫に入るアナウンスも耳に入らず、危うく車庫まで行ってしまいそうになりました。(^^;
平凡社ライブラリー 552 2005年9月初版 1,900円